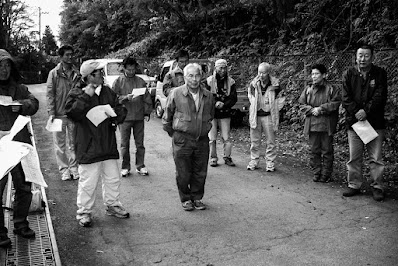神田川の橋からのぞいたら鴨が逆立ちをして水草や水中にいる生物をあさっていた。ちょっと面白い格好して愛らしくもあるが、いままでそれを見てもそういうものだと思っていた。なぜなそういう格好をするのかを知らなくて、ボーっとしているのを怒られないようにNET検索してみたら、水に潜れないということなんだそう。
越冬のためにやってくる鴨をこの暑さの中で見ることができたのは、「冬が近くて」涼しくなる幸運の使者ともなる。しかし気の毒なことには、神田川の切り立った三面張り水路では、堆積の少ない流れに薄汚れた水草が揺らめいているだけで、昔ながらの「川」であれば繁殖しそうな「動物性たんぱく質」は、鴨の口に入りそうもない。せっかく遠くから訪ねて来てもこれでは栄養失調だ。
これも都市の悲哀なのか、豪雨をしのぐ災害対策が優先されて生物の生息環境に手を回すことはほとんどない。上流部には環境に配慮した造成がされているところもあるが、都会部が近くなるにつれて有様は水路オンリーといった格好だ。(新宿に「親水テラス」施設がある)
鴨の気の毒さは他にもある。「他の野鳥に比べて動きが遅く、捕まえやすい鳥であることが災いして、利用しやすい人や騙されやすい人の比喩として「カモ」と使われること。「ネギしょってこい」はよく使われていた。いまの社会状況はずっと深刻で「カモ」にされることは、これでもかというほどある。鴨にとっても非常に不名誉迷惑な話だ。
元々は徳川将軍家や有力大名家が行っていた伝統猟で、明治時代以降は皇室が維持保存を行っている鴨場の猟では「貢献」している?
―鴨場(埼玉と新浜)は、内外の賓客接遇の場としても実施、毎年11月15日から翌年2月15日までの狩猟期間に招かれた閣僚、国会議員、最高裁判所判事や各国の外交使節団の長等がこの独特の技法で自ら鴨を捕獲…―
維持保存しているとのことだが、人間の食餌から解放されたのはよしとしても、我が方の身の上を考えると「税金使用」だからね。
―訓練したアヒルを使い鴨を猟者が潜む直線的な細い水路に誘導し、飛び立つ瞬間を網で捕獲する。水路で飛翔方向が限定されるため、網を振るだけで子供でも容易に捕獲が可能である。その後捕獲した鴨は国際鳥類標識調査に協力するために種類・性別などを記録し、標識(足環)をつけ放鳥される。―
のだって。三番瀬で野鳥観察をつづけている団体(三番瀬セットワーク)はあるけど~