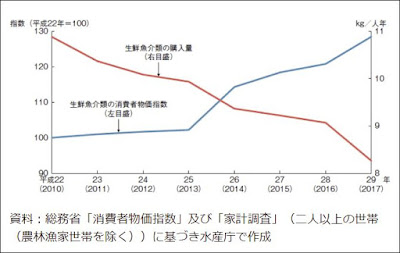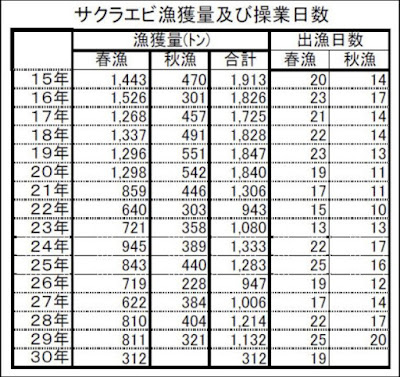湯河原のミカン畑から落ちて転がり、川から海に流れたミカンをクロダイが食べるという。房総の方ではクロダイ釣りの餌にスイカを使うということもある。魚の知恵なのか進化か生き残りかにかかることなのかわからないが、なにかの必要条件に迫られて食を満たしているのだろう。クロダイのように悪食と言われる魚たちも、およそ自然らしさを遠ざけられてしまった海辺で、さんざんな目にあいながら生き続けているのだろう。
悪食の定義が「人が食べないもの」を食うということだが、魚に対して例えばイワナが悪食、クロダイが悪食…などとよく言う。でもそういう人間様ほど悪食なものはいないと私は思う。「人が食べないもの」との定義でしても、新型コロナで話題のコウモリを食ってしまうのも人間様だし。魚のえさになるアミやイワシなどまで食い尽くしているのも人間だ。果ては(魚)卵類まで「美味しく」いただく。「人が食べるもの」の範疇にここまで入っていて、人間は悪食でないと胸を張れるわけがない。
海岸エリアの利用で開発という名の環境破壊と、熾烈な漁獲量確保の競争でどれだけの魚類を再生困難な環境に追い込んだのか。仕掛けたのは人間の方だ。遅きに失するほどでも、ようやく成長の有りようが問い直されてはきた。自然のダイナミズムな変容にマッチした対策が必要なのだろうと思う。
アムール川から流氷と一緒に運ばれる鉄分などの栄養は、親潮に乗って運ばれプランクトン繁殖のもとになっていた。おそらくは気候変動の影響をうけて「流氷が減る」ことで、運ばれにくくなる、否定的な動きになったのではないか。北海道での魚類海藻類の水揚げが減っているのはこうした背景があると思われる。
アムール川が運び、大陸棚に堆積した鉄は、この二つの海洋の動きによってオホーツク海の中層を通り、千島列島付近の潮の動きによって広く親潮の表層へと運ばれていることがわかってきました
われわれはまだこんなところにいる。これは悪いことではないし、好ましいことだがこの先が思考停止ではまずい。
<主なフルーツ魚>
鹿児島県:柚子鰤王
大分県:かぼすヒラメ
香川県:オリーブはまち
愛媛県:みかんブリ
広島県:レモンはまち
三重県:伊勢まだい *伊勢茶を使用