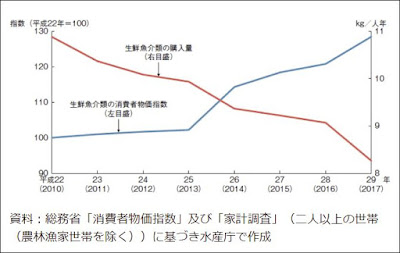高齢者の自動車事故で「免許証の返納」を考えるべきとの自己責任論が幅を利かせたかと思ったら、今度は国が年金を払えないからから「投資」をやれと言わんばかりの自己責任論が振りまかれる。
高齢者の足の問題をどうするかという言葉は前置きにあっても、その対策が出されなくては高齢者が困るばかりだろう。返納しても無免許で運転することまでが想定されてくる。地方でも都心でも独居の老人が増えている現状に、政治が先行的に策を立てるのかという問題だろう。
年金財源が賄いきれないよということを、政府や官庁がわかっていて、反発が強いから選挙対策のために財源状況を知らせず、だんまりを決め込むのはえげつない。あまつさえ年金財源が足りないからやれ働けの投資しろのという政治的無責任な考えかたは許されない。
「受け取り年金が少ない」年代の賃金を上げるだけでも効果はあるだろう。非正規雇用をどんどん増やし、超過勤務をさせても実態通りに払いもせず、払ったとしても年金財源にはすべて反映するわけではない。こんな組み立てでは年金財源は減るばかり。
「普通に暮らせる型」を考えどういう手を考えて打ちだすのかが政治の責任と言うものだろう。そこを黙って対応しなければ崩壊することしかない。年金財源は企業や国からの資金も入っているわけで、支え手が少なくなって…などと消費税導入に使ったインチキ論法をまた使うのは振り込め詐欺に等しい。